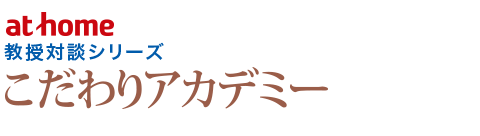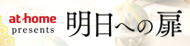こだわりアカデミー
「タバコ依存」は「薬物依存」。 ニコチンには「興奮」「鎮静」の 「二相性の効果」があるんです。
ニコチンは依存性薬物
浜松医科大学精神神経科助教授
宮里 勝政 氏
みやさと かつまさ

1944年沖縄県那覇市生れ。69年広島大学医学部卒業後、東京慈恵会医科大学入局。80−82年、アメリカ合衆国国立薬物乱用研究所へ留学し、薬物依存症を実験的に研究した。専攻は精神医学。医学博士。著書に「アルコール症の臨床」(新興医学出版)、「メンタルヘルス事典」(中央法規出版、共著)、「青年心理学ハンドブック」(福村出版、共著)、「精神療法」(ライフサイエンスセンター、共著)がある。今年初めに岩波書店より発行した著書「タバコはなぜやめられないか」は、タバコ依存を薬物依存の観点から客観的に分析し、わかりやすく解説している。
1993年9月号掲載
依存性薬物の作用は「鎮静」「興奮」「知覚変容」
──先生は薬物依存のご研究を長年続けておられますが、そもそも「薬物依存」とは何ですか。
宮里 「薬物の精神効果を味わいたいという強い欲求があり、繰り返し取っているうちに耐性ができたり、やめると退薬症候(昔でいう禁断症状)が現れたりする状態」を「薬物依存」と言い、それが、身体・精神・社会的役割行動に著しい影響を及ぼすようになり、何らかの対応を必要とするほどになると「薬物依存症」と呼びます。「やめようと思ってもやめられなくなった状態」と言ってもよいでしょう。こうした状態をつくり出す物質(薬物)を「依存性物質(薬物)」と言い、大きく3種類に分けられます。
一つは、脳の働きを穏やかにするもの、すなわち鎮静・抑制効果のある物質です。アルコール、モルヒネ、ヘロイン、精神安定剤、睡眠薬等、中枢神経抑制薬と言われるものがあります。
二つめは、それとは逆に、脳の働きを高める作用、興奮作用があるもので、コカイン、覚醒剤が代表的です。
もう一つは、幻覚等の知覚変容を起こす物質で、マリファナ、LSD、メスカリン、シンナー等があります。
これらの依存性薬物は、体内に入ると、脳に入り、脳の中枢神経組織に作用します。そして多幸感、つまり陶酔感とか快感と言ったらわかりやすいかもしれませんが、そういういい気持ちにしてくれるんです。だから使用を繰り返すうちに、その多幸感をまた味わいたい、またいい気持ちになりたいと思うようになってくる。
そして「薬物依存」が始まるわけです。
──甘いものや辛いものが好きでやめられない、という理由とは基本的に違うわけですね。
 サイト内検索
サイト内検索