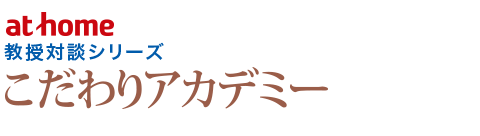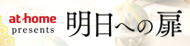こだわりアカデミー
「奥の細道」は俳文の極み。 芭蕉の句は、イメージを無限に拡げてくれます。
現代に甦る松尾芭蕉
山梨大学名誉教授
伊藤 洋 氏
いとう ひろし

いとう ひろし 1940年、山梨県生れ。62年山梨大学工学部電気工学科卒業、67年、東北大学大学院工学研究科電気・通信工学専攻博士課程修了。同年、山梨大学工学部講師、助教授を経て、78年教授。95年、総合情報処理センター長。99年学部長。2002年副学長。共著に『核の時代をどういきるか』『まるごと図解 最新コンピューターネットワークがわかる』など。また、『えんぴつで奥の細道』(ポプラ社)を監修するなど、松尾芭蕉に関する国内最大級のデータベース「芭蕉DB」の運営者としても知られている。
2006年8月号掲載
「俳句」は不明確な世界。だからこそ膨らむ想像の世界
──それにしても、実際に「奥の細道」に触れてみると、実にすばらしい文章ですね。
伊藤 そうですね、「俳文の極み」です。
そもそも俳句は説明文などとは違って、事実をこと細かにすべて伝える必要はありません。言葉がそぎ落とされた、実に不明確な世界です。一方、近代人はものを読み伝える際には、ニュース原稿のようにいつもメッセージを正確に受け取る・送る努力をさせられてきました。いかに正確な表現で、事実をありのまま伝えるかを訓練されています。
例えば、「古池や蛙飛び込む水の音」を文面に忠実に理解しようとすると、蛙が水に飛び込んで水音がした、だから何なの?ということになりますが(笑)、俳句として考えると、人々がそれぞれの脳裏で各々の美観で想像した情景を創り上げる、いわば無制限の世界が拡がります。
いい加減な表現であるからこそ、無制限にイメージを拡張していける。また、そこから大きな世界に包まれている、という安心感のようなものが発生する。これが俳句の良さではないかと思います。
一方、現代人の社会生活は言葉や思想を明確にしなければいけないという合理的な世界の連続です。自由にイメージを拡大していける俳句の世界は、管理社会を生きてきたものにとっては、ほっと救われるような、自由で豊かな想像の世界といえるのではないでしょうか。
でも、もし会社で俳句のような表現を使用していたら、上司も部下も何をいっているのかがよく分らない、困ったことになるのですが…。
──(笑)。確かにそうですね。
 |
| 芭蕉ゆかりの墨田川沿いには句碑が点在、散策者を楽しませている |
 サイト内検索
サイト内検索