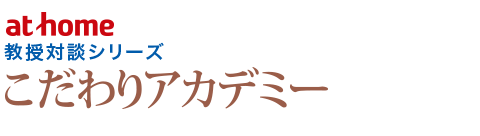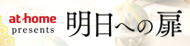こだわりアカデミー
日本のまちの色は賑やかさや活気を感じる一方、 『騒色』の弊害もあります
環境を左右する「色」の不思議
神奈川大学人間科学部人間科学科教授
三星 宗雄 氏
みつぼし むねお

1950年福島県生まれ。74年千葉大学人文学部人文学科(心理学専攻)卒業。81年東京大学大学院人文科学研究科博士課程(心理学専門課程)単位取得退学、博士(心理学)。86年ミシガン大学Department of Ophthalmology(眼科)研究助手、87年神奈川大学外国語学部専任講師、89年同大学外国語学部助教授、95年同大学外国語学部教授。2007年同大学人間科学部教授に就任、現在に至る。主な著書に、『色の心理学』『環境色彩学の基礎』(いずれもマックローリン出版)、『色彩の快:その心理と倫理』(御茶ノ水書房)など。
2015年6月号掲載
三星 まず、1981年の「東京都バス事件」が騒色公害事件の第1号です。
この事件は、それまで白地に青の帯だった都バスの色を、より目立たせたいとの意向から、黄色地に赤というボディのバスが走り始めたというもの。多くの人から「目立ち過ぎる」「下品」「イライラする」などの声が挙がったそうです。結局、現在の黄緑色とクリーム色に落ち着きましたが。
──確かに、公共輸送機関としてはイメージがあまり良くなかったでしょうね。2つ目は?
 |
 |
| 現在の都バス(東京・新宿にて、写真上)〈写真提供:三星宗雄氏〉。「東京都バス事件」で輪台になった黄色地に赤のバス(写真下) |
三星 1985年の「世田谷マクドナルド事件」です。12階建てマンションの屋上に巨大なネオンサインを取り付けるという計画が持ち上がり、住民間で激しい反対運動が繰り広げられました。結果、赤色ネオンは使わないことで合意に至ったわけですが、この事件を機に、まちの景観に対する住民の意識は急激に高まっていったのです。
──では3つ目の事件は?
三星 1986年の「高崎ビックカメラ事件」です。これは、開店直前になって工事シートを外したところ、店舗の外壁すべてがオレンジの蛍光色だったという驚くべきもので、住民から「ノイローゼになりそう」「建物が恐ろしい生き物のようだ」などの苦情が次々と寄せられたそうです。行政が全国で初めての改善勧告を出したことでも話題となりました。
──行き過ぎはやはり・・・といういい例ですね。
「色彩ガイドライン」の普及で、調和のあるまちづくりを
──まちに賑やかさや活気が必要だということは分かりますが、こうしたことは、できてから直したり、取りやめたりするのは難しいですし、無駄ですね。
 |
| 『色の心理学』(マックローリン出版) |
三星先生は同大学を退職されました。今後は「東京キャリコ認知科学研究所」で、実際の現場における色彩・認知の問題についてご研究を続けられます。
 サイト内検索
サイト内検索