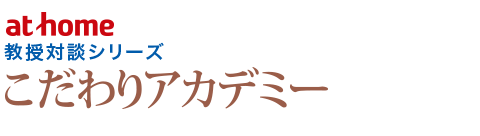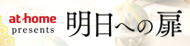こだわりアカデミー
日本の庶民観光の始まりは「お参り」。 「お伊勢参りブーム」に乗って 旅行業の基礎もつくられました。
観光はいつ生まれたか
社会学者 立教大学観光学部教授
前田 勇 氏
まえだ いさむ

1935年、東京都生れ。59年、立教大学文学部心理学科卒業後、同大学心理学研究室を経て、66年同大学社会学部産業関係学科講師。67年観光学科設置に伴い移籍後、助教授を経て75年教授。98年観光学部・大学院観光学研究科設置により移籍、現在に至る。社会学博士。立教大学観光研究所所長、日本観光学会評議委員、日本能率協会・サービス向上推進全国大会実行委員長、日本道路公団・関東ハイウェイ懇談会座長等多数の役職を兼務。主な著書に『実践・サービスマネジメント』(89年、日本能率協会)、『観光とサービスの心理学』(95年、学文社)、『現代観光学キーワード事典(編著)』(98年、学文社)など多数。
2001年4月号掲載
「一点豪華主義」で旅の思い出が倍増
──現代人の観光は、昔に比べて目的や内容が多様化、複雑化しています。そうした中で、少しでもいい旅、いい観光をするために、何かアドバイスはありますか?
前田 旅に出るということは、非日常を経験するということで、普段は気が付かない新しい発見、勉強ができるものです。ですから、できるだけ普段の生活を切り離して過ごすようにすることが大切だと思います。旅行中でも携帯電話で仕事の指示を出すなんて、もっての外です。
旅をより印象深いものにするためには、例えば、一点豪華主義を心掛けてみてはいかがでしょう。宿泊も食事も乗り物も見物も、すべてある程度「そこそこ」ではなく、予算を増やさないままで、どこか一つに寄せ込んでやるんです。食事だけは豪華にするとか…、わずかな工夫で思い出が倍増するはずです。
あと、これは要望ですが、長期休暇を取ろうとすると、どうしてもお盆や正月、ゴールデンウィークというように、ほとんどの国民が一時期に集中してしまう。バラバラに長期休暇を取れるようにしてほしいですね。
──旅行費用も高くなりますし、渋滞も多くなって、ロスが多いですからね。
先生は、教鞭を執られるほか、数々の公職を務められ、日本の観光業の発展にも貢献されていらっしゃいます。今後のご活動予定は?
前田 立教大学は国内初の観光学科(当初は、社会学部の一学科だったが、98年に改組拡大で独立、観光学部に。同時に大学院も併設)を設置した大学で、これまで数多くの人材を輩出してきました。今後さらに、21世紀の観光業界を担う人材の育成に力を注ぎたいですね。
──いまや観光業はグローバルな産業です。国によっては、観光が経済を支えているところもあります。しかし国際的に見て、日本人の観光や余暇に対する認識は、まだまだいろいろな意味で薄いように思います。先生には、そうした意識の改革も含め、ますます広範なご活動を期待しております。
本日は、ありがとうございました。
 サイト内検索
サイト内検索