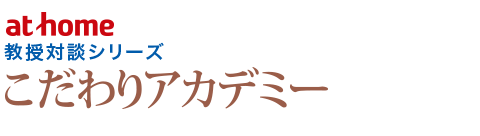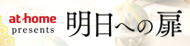こだわりアカデミー
日本の庶民観光の始まりは「お参り」。 「お伊勢参りブーム」に乗って 旅行業の基礎もつくられました。
観光はいつ生まれたか
社会学者 立教大学観光学部教授
前田 勇 氏
まえだ いさむ

1935年、東京都生れ。59年、立教大学文学部心理学科卒業後、同大学心理学研究室を経て、66年同大学社会学部産業関係学科講師。67年観光学科設置に伴い移籍後、助教授を経て75年教授。98年観光学部・大学院観光学研究科設置により移籍、現在に至る。社会学博士。立教大学観光研究所所長、日本観光学会評議委員、日本能率協会・サービス向上推進全国大会実行委員長、日本道路公団・関東ハイウェイ懇談会座長等多数の役職を兼務。主な著書に『実践・サービスマネジメント』(89年、日本能率協会)、『観光とサービスの心理学』(95年、学文社)、『現代観光学キーワード事典(編著)』(98年、学文社)など多数。
2001年4月号掲載
庶民の観光は、平安時代の熊野詣(もうで)が始まり
──わが国の観光の歴史はいつ頃から始まったのでしょう?
前田 旅の歴史を遡ってみると、まず「生きるための旅」が最初です。人々は食糧や生活の場を求めて、移動しながら生活していました。その後、大和朝廷の登場で「命令される旅」が出現します。支配する者とされる者という構図ができ、支配者達は「領地に出向く旅」、被支配者達は「都へ税金を納めに行く旅」が始まったわけです。さらに支配者層の中から、自分の自由意志で「自ら好んで行く旅」というものが広まっていったと思われます。
──支配層の人達から始まったんですね。当時、彼らはどういうところに行ったんですか?
前田 お花見や温泉などです。特に温泉は、当時から健康に良いことが分っていたようで、七世紀頃に仲哀(ちゅうあい)天皇の妃・神功(じんぐう)皇后が好んでよく行ったという話も伝えられています。
──庶民の観光が始まったのはいつからですか?
前田 平安時代中期、最初は信仰からくるものでした。いわゆるお参りの旅ですね。一番古くは和歌山県南東部から三重県南部にかかる熊野山への参拝、「熊野詣」です。ここは地形的に険しい山間部で、現在も神の宿る聖地として敬い崇められています。当時は、行き交う参拝者の数がまさに蟻の行列のようだということで、「蟻の熊野詣」といわれるくらい流行したのです。
──奥州平泉の藤原秀衡も、熊野に参拝したという話を聞いたことがあります。それほど広まったわけですね。
前田 そうです。しかし室町時代になると、信仰の中心は伊勢神宮(三重県伊勢市)へと移っていきます。同じ御利益があるのなら、険しい山道を行く荒行のような熊野詣よりも、平坦な道を行く伊勢神宮が好まれるようになったようです。
そして、さらに多くの庶民が観光に出掛けるようになったのは、江戸時代に入ってから。国内の争いの時代が終り、庶民が平穏な生活が送れるようになったからです。また、五街道や宿場などのインフラ整備が行なわれ、旅をしやすい環境になったことも後押ししていますね。

 サイト内検索
サイト内検索