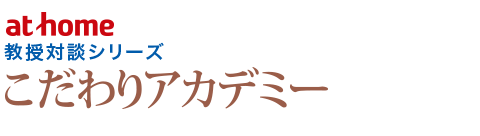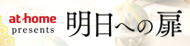こだわりアカデミー
時代の変化とともに急増する新たな心の病。 精神科外来を通して、見えてくる現代社会とは…。
現代社会と心の病
防衛医科大学校精神科教授
野村 総一郎 氏
のむら そういちろう

1949年、広島県生れ。74年、慶應義塾大学医学部卒業。米国留学などを経て、88年、藤田学園保健衛生大学精神科助教授、93年、立川共済病院神経科部長、同年同病院内にMPUシステムを整備。97年より現職に。医学博士。主な著書に『うつ病の動物モデル』(84年、海鳴社)、『うつ病を知る−軽症化の時代に』(93年、日本アクセル・シュプリンガー出版)、『もう「うつ」にはなりたくない』(96年、星和書店)、『「心の悩み」の精神医学』(98年、PHP研究所)、共著に『ウツの気分とつきあう方法』(94年、河出書房新社)など多数。
2002年3月号掲載
精神医学の大幅な進歩に伴い多軸的診断の方向へ
──深刻化する青少年犯罪の問題や、マスコミなどでも取り上げられている「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」、「ひきこもり」など、最近、心の病が非常に話題を集めています。先生のご著書『「心の悩み」の精神医学』を読ませていただいたのですが、まるで現代を別の切り口から見ているような感を覚えました。
その一方で、私がこれまで抱いていた精神の病や医学のイメージとは、随分と様子が変ってきているような気がしますが…。
野村 近年、精神医学は大幅に進歩し、世間で思われているよりも、精神科医がずっと役に立つ存在になってきたんですよ(笑)。かつては医学界内からも、「精神医学は学問としては面白いけれど、治療ということになるとちょっと…」などといわれていましたからね。
──いえいえ、私は昔から社会に貢献している医学だと認識しておりました(笑)。
変った、というのは、具体的にはどのように?
野村 一言でいえば、学問的な進歩と医療システムの整備がうまく噛み合った結果、とでもいいましょうか…。
まず、神経医学や脳科学の大幅な進歩により、脳内物質のコントロールが可能になり、薬も変りました。また、診断技術、計測技術の発達や、ITの発達も随分と精神医学の進歩に影響を及ぼしているんですよ。
──心の治療発展の陰に、科学ありというわけですか。
野村 ところが一方で、面談などを重視する日本の伝統的心理療法が現在、欧米などでも再評価され始めたんですよ。
──進歩しながらも、反面、過去の治療法が見直されている…?
野村 これまでは心理学的見地か、それとも精神医学か、どちらかに偏ることが多かったのです。しかし現在では、これらを2本立てでやっていこうという考えが広まりつつあります。多軸的に患者に向き合うことで、精神医学の治療力も随分高まっているんですよ。
──さまざまな治療法が共存できるとは!ここが他の医学とは違うところですね。
精神の病に対する人の意識なども変りつつあるんでしょうか。
野村 もちろんです。1995年に精神保健福祉法が施行され、精神障害者をケアするシステム整備が急速に進んだこともあって、以前に比べると、随分人権意識が高まってきました。
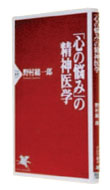 |
| 『「心の悩み」の精神医学』(PHP研究所) |
 サイト内検索
サイト内検索