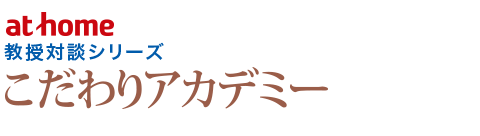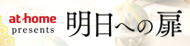こだわりアカデミー
「おいしさ」と「こく」に科学的に迫る!
「うまさ」の科学
栄養化学者 京都大学農学研究科食品生物科学専攻栄養化学分野教授
伏木 亨 氏
ふしき とおる

ふしき とおる 1953年、京都府生れ。75年京都大学農学部食品工学科卒業、80年同大学院博士課程修了。同大学同学部助手、助教授を経て、94年より現職。85年から86年まで米イーストカロライナ大学医学部へ留学。89年、日本農芸化学会奨励賞受賞。現在、日本栄養・食糧学会理事、日本香辛料研究会会長、日本動植物細胞工学会評議員も務める。専門は食品・栄養化学。おいしさの脳科学、自律神経と食品・香辛料、運動と栄養など、幅広い研究を行なっている。著書に『魔法の舌』(96年、祥伝社)、『グルメの話 おいしさの科学』(2001年、恒星出版)、『ニッポン全国マヨネーズ中毒』(03年、講談社)、編著に『うまさ究める』(02年、かもがわ出版)など多数。
2003年4月号掲載
「こく」も「おいしさ」もバランスが命
──これまでのお話で、「おいしさ」とはどういうものか分りました。先生は、その「おいしさ」の延長にある「こく」についても、ご研究されていらっしゃいますよね。言葉で説明するのは難しいと思いますが、「こく」とは一体どういうものなのでしょうか?
伏木 実は私もそれを知りたくて、昨年「食べ物のおいしさと『こく』」というシンポジウムを開催したんです。その結果、「こく」という概念が確かにあるということや、それがほめ言葉だということ、人によって使う範囲が違うことなどが分りましたが、大体皆同じ認識を持っているということが分りました。
──といいますと?
伏木 1つは、ずばり、生きるために重要な栄養素が豊富な「こく」です。ダシや油、砂糖などに、多くの人は「こく」を感じています。それらが第1の「こく」です。
 |
| お吸い物は、第2の「こく」を感じさせる代表作 |
第2の「こく」は、それだけでは「こく」を生むことはできないけれど、第1の「こく」を連想させるもの、「こく」の面影を残しているものです。
──例えば?
伏木 日本のお吸い物です。特に名人の作るお吸い物は、シンプルながらも洗練されています。「飲み応えがある」というわけではないけれど、ダシや砂糖、醤油などの味が第1の「こく」を連想させる。栄養はそれほどないはずなのに、味に深みを感じさせる−−そういうものが第2の「こく」です。
それから最後に、食べ物から離れてイメージとして使われる「こく」があります。例えば、「『こく』のある表現」「『こく』のある人」といった使われ方が、第3の「こく」です。
──なるほど。でも、どうして私達は食べ物に「こく」を求め、「こく」があるとおいしいと思うのでしょうか?
伏木 それは、先程も申しましたが、「こく」が人間にとって重要な栄養素に関わる味だからです。人間が生きるために必要な栄養素がバランスよく入っている。だから、私達は「こく」を求める感覚を持っているのだと思います。
──なるほど。「こく」もバランス、「おいしさ」もバランスですか。
伏木 つまり、「こく」とは「おいしさ」をイメージ化、抽象化したものといえるかもしれません。
 |
| 『ニッポン全国マヨネーズ中毒』(講談社) |
 サイト内検索
サイト内検索