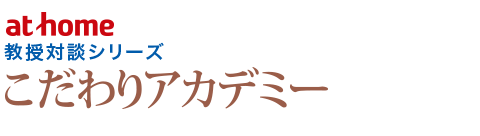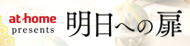こだわりアカデミー
発掘した遺跡のデータから 飛鳥の人々の衣・食・住を再現したいと思っています。
神話から史実へ−飛鳥の古墳を調べる
考古学者 京都橘大学教授
猪熊 兼勝 氏
いのくま かねかつ

1937年、京都府生れ。64年、関西大学大学院文学研究科考古学専攻修士課程修了、92年、奈良国立文化財研究所飛鳥資料館学芸室長、研究指導部長などを経て、98年より現職。大学在学中から平城宮跡、藤原宮跡の発掘に参加し、マルコ山古墳、キトラ古墳、イースター島などの発掘を手掛ける。キトラ古墳では83年に初めてファイバースコープを使用して壁面下に「玄武図」を発見、その後、98年にキトラ古墳再調査で学術調査団長を務め、「星宿図」等を発見した。また、87年に阿武山古墳の被葬者が藤原鎌足であることを突き止め、日本書紀の記述を証明した。著書は、『埴輪』(講談社)、『飛鳥の古墳を語る』(吉川弘文館)など。
2006年3月号掲載
「神話」と「歴史」をつなぐ飛鳥の遺構
——先生は飛鳥時代のご研究の第一人者と伺っております。日本史ファンの多くは特にこの古代「飛鳥」時代に興味が強いといわれますが、この時代の魅力とは一体何でしょうか?
猪熊 この時代は、ちょうど「神話の世界」と「史実である歴史の世界」の間にあって、文化や社会が大きく変った時期なんです。このわずか百年足らずの間に、「聖徳太子の登場」「大化の改新」「壬申の乱」なども起きていますしね。

——異文化も入ってきて、ドラマチックな事件がたくさん起きた時代ですね。
猪熊 そうですね。
また、われわれ研究者にとっても、非常に研究対象にしやすい時代です。
というのも、飛鳥時代の中心地であった奈良は、この時代以降大規模な開発がほとんど行なわれなかったため、1m程掘ると建物の基礎の部分が出てきます。つまり、地表から1mのところに聖徳太子の歩いた道や、藤原鎌足が駆けたところ、蹴鞠の跡などが出てくるわけです。
これが京都などになると、事情が変ります。京都は794年に遷都されて以降、長い間都でしたから、人々の営みの形跡が層のように積み重なっていますからね。
——なるほど。
猪熊 また、飛鳥・大和全体にいえることなんですが、この辺りを発掘してみると『日本書紀』や『続日本記』に記述されている事例を裏付けるようなものが出土され、『日本書紀』の世界が事実であったことが分り大変面白いんですよ。
 |
| 国営奈良歴史公園甘樫丘地区で発見された蘇我蝦夷・入鹿邸跡。その他、資料の発見にも期待が寄せられる <奈良県高市郡明日香村にて。資料提供:猪熊兼勝氏> |
 |
| 飛鳥の古墳を語る |
 サイト内検索
サイト内検索