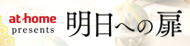こだわりアカデミー
われわれに役立つ自動翻訳機ができるのは 21世紀の中頃になるでしょうね。
ゲーム少年から人工知能研究者へ
慶應義塾大学環境情報学部助教授
冨田 勝 氏
とみた まさる

1957年、東京生れ。81年、慶應義塾大学工学部数理工学科卒業後、アメリカ・ペンシルバニア州カーネギーメロン大学コンピューター科学部大学院留学。ノーベル賞学者H.サイモンの研究助手として人工知能の研究に従事。83年、修士号、85年、博士号取得。カーネギーメロン大学自動翻訳研究所副所長、同大学コンピューター科学科助教授も兼ねる。トミタLR法という高速構文解析法を考案するなどの功績が評価され、88年、レーガン大統領より米国立科学財団大統領奨励賞を受賞。国際論文誌“Computational Linguistics”“Machine Translation”編集委員も務める。音楽家・冨田勲氏は父親。著書に「ゲーム少年の夢」(1991.講談社)がある。
1994年2月号掲載
インベーダーゲームが人工知能(AI)との出会い
──先生は、人工知能(AI)の研究で博士号まで取っておられますが、その分野に進むきっかけになったのはなんと「インベーダーゲーム」だそうですね。
冨田 はい。インベーダーゲームが私の人生を変えました。
ちょうど大学2年の頃に大流行しまして、もともと小さい頃からゲームは好きでしたので、すっかりその虜になってしまったんです。かなりの時間とお金を注ぎ込みましたね。それが高じて、ゲームの中身、すなわちプログラムに非常に興味を持つようになったんです。これがコンピュータ科学との出会いになりました。
──プレーヤーとしてもかなりの達人で、当時その世界では「名人」と呼ばれていたそうですね。いろいろな技も持っていたとか…。
冨田 ええ。例えば「300点UFO」といって、ボーナスポイントの高いUFOばかりを狙って撃ち落とし、高得点をあげるという技があります。これは、後には一般に広く知れわたり誰でも駆使するようになりましたが、当初は「神技」と呼ばれたんです。しかし、初期のインベーダーゲームの得点の上限が低かったため、そういうことをやっているとすぐに得点が上がりゲームオーバーになってしまう。そこで他にも次々に新たな技を考えだしたんです。例えば、コンピュータプログラムのミスを突いて、画面上に奇妙な現象を起こしたりする「レインボー」とか「インベーダーの化石」と呼ばれた技もありました。
しかし、こうした隠し芸の種も段々知れわたるようになりましたので、最後にはいかにギャラリーを楽しませるかということで、とうとう手を使わずに足でプレーするという大技を開発したんです。
──それは究極ですね。(笑)
冨田 足だけで、普通の人が手を使うのと同じくらいのレベルのプレーができるようになり、私が足技を始めると、野次馬でものすごい人垣ができるくらいでした。
──まさに「名人」の名を欲しいままにしたわけですね。
自作ゲームソフトを秋葉原で売り歩く
──そうした遊びが、コンピュータとのつながりを深めていったわけですか。
冨田 ゲームが上達するにしたがって「ここにこんなルールがあればもっとおもしろくなるだろうな」などと思うようになりまして、ついに、自分でつくるようになったわけです。
ちょうどその当時、アメリカで「APPLE II」という、今でいうパソコンの元祖みたいな画期的なコンピュータが発売されたので、早速購入し、英語は大の苦手だった私が、マニュアルを全部読み切るほど熱心に勉強しまして、数多くのゲームプログラムをつくりました。
──お小遣い稼ぎに、そういうソフトを売ったりしていたそうですね。
冨田 ええ。当時はまだソフトウェアに対する認識が低く、ゲームソフトをまともに扱う会社もなかったので、自分で売り歩きました。フロッピーを持って秋葉原に行き、マイコンショップを一軒一軒回って、一番高く買ってくれるところに売っていました。
──漢字ワープロも開発したとか…。
冨田 「アップル漢字システム」といって、今から見ればものすごく原始的なシステムですが、当時はまだ「ワープロ」という言葉もないくらいで、日本語が扱えるものは大型コンピュータに限られていたんです。ですから、当時としてはセンセーショナルで、いくつかの雑誌にかなり派手に取り上げられたりしました。
その頃から、もっと知的なゲームができないものかと考えるようになり、「将棋」のプログラムづくりに取り組んだことが「人工知能」との出会いにつながっていったわけです。

コンピュータには複雑すぎる「将棋」の思考
──これは今のところ未完成ということですが。
冨田 コンピュータには複雑過ぎるということです。つまり将棋をする場合、一手指すごとに「こうしたらこう来る、そうしたらこうして、こう来て、こうすれば・・・」という具合に、人は常に何手あるいは何十手も先を読んでいるわけです。初心者でも5手先を読むと言われています。有段者は30手くらい、プロになると80手くらい先を読んでいるようです。
一つの局面で考えられる指し手の中で、よさそうな手はだいたい30通りぐらいあると思いますから、その次の相手の手まで読むと30×30で900通りということになりますね。
──じゃあ、5手先だと30の5乗ということですか。
冨田 そういうことです。それだけの膨大な数の局面を全部比べて一番いい手を選ぶわけです。しかも人間は数分の間にそれをやっている。これをコンピュータでやったら大変な作業です。一手指すのに膨大な時間がかかってしまう。
その点、人間はすごいなと思うのは、約30通りの指し手があるにもかかわらず、実際には最初から1手か2手にしぼり込んで考慮しているわけです。あとの手は候補にも挙がらず無視されています。
つまり、コンピュータに人間と将棋をさせるには、人間の思考過程をインプットしなければだめだということが分かったんです。
──人間の脳のメカニズムってすごいですね。
冨田 本当に素晴らしいと思います。それで最初は心理学の本なんかを探しては読んでいたんですが、どうもコンピュータ将棋には役立ちそうもないと分かり、いろいろ調べているうちに「人工知能」という学問の存在を知り、これぞ私の探していたものだということで、この道に進んだわけです。
──「人工知能」の研究というのは、どういうものですか。
冨田 この分野は、最近2分化しています。簡単に言うと、一つは、われわれ人間がもっと便利になるようにコンピュータを賢くしていこうという分野。もう一つは、人間の思考のプロセス、意識や記憶等の物理現象といったものをコンピュータでシュミレートし、脳の構造を明らかにしようという分野です。
──先生が今取り組んでおられる「自動翻訳」は前者ですね。ご研究はどの程度まで進んでいるんですか。
冨田 今やっているのは音声翻訳といいまして、マイクでしゃべった声を認識させ、それを翻訳して音に合成して出す、というものです。
今の段階では、まず、レストラン、税関、病院等、会話の場所をかなり限定し、使える単語の数も500くらいで、かつ、吃ったり訛ったりせずはっきりしゃべる、という条件付で、8割方の確率で10秒以内に答えが出る、という状況です。
とにかく、音声の認識をするのがべらぼうに難しいんです。われわれの役に立つものができるのは、21世紀の中頃になるだろうと思っています。
──一つの単語でもいろいろな意味を持つ場合がありますし、同じ発音でもまったく異なる単語もありますから、機械にそれをどう把握させていくかというのも難しいテーマですね。
冨田 そうです。辞書みたいに単語の容量さえ増やせばそれですぐ役に立つというものではありませんから、精度を上げながら、拡大していくというのは並大抵ではありません。何か根本的に新しい手法が見出されない限り、少しずつ地道につくっていくしかないんです。
次の夢は専門分野を2つにすること
──「ゲーム少年」から「人工知能研究者」になられるまでの楽しいお話ばかりうかがいましたが、ご著書「ゲーム少年の夢」には、いろいろな努力や苦労をされた様子も書かれてあります。特に私が素晴らしいと思ったのは常に何か夢を持ち、それを着実に実現させてきているという点です。そこで、最後に、次なる夢がありましたらお話し願えませんか。
冨田 人工知能の研究以外にもう一つ専門分野を持ちたいと思っています。昔から専門分野は2つにしようと思っていたので、近いうちに実現するつもりです。
──それはまた、どういう理由で?
冨田 日本では一般に、学者とか研究者というと、「学者馬鹿」とか「ネクラ」というような良くないイメージがあります。もちろんそうでない人も大勢いますからこれは偏見なんですが、一方ではそれが変な美学みたいなものになっている。これでは次代を担う研究者が育たなくても無理はない、今の若者はカッコ悪いのは嫌いですからね。これが日本の基礎研究のレベルがなかなかアメリカに追いつかない理由のひとつではないかと思っています。
学者とか研究者のイメージアップを図っていくためにも、まず私自身が「学者馬鹿」や「ネクラ」にならないように気を付けていきたいと思っています。そのためにも1つの分野に固執しないで、柔軟な生き方、考え方をしていきたいんです。専門分野を2つ持っていれば、視野も活動範囲も、ものすごく拡がりますからね。
──なるほど。まさに新しい時代を築いていくエースになりそうですね。ますますのご活躍を期待しています。ありがとうございました。
 サイト内検索
サイト内検索