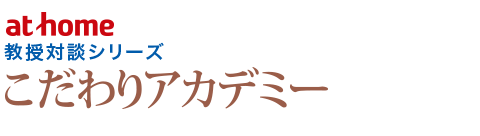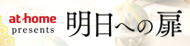こだわりアカデミー
祭りは本来、神様を「祭る」という事。 現代では人々を結び付ける重要な役割を果たしています。
日本人と祭り
国文学者・民俗学者 盛岡大学文学部教授
大石 泰夫 氏
おおいし やすお

おおいし やすお 1959年、千葉県生れ。83年、國學院大學文学部文学科卒業、89年、國學院大學大学院文学研究科博士課程修了。89年より武蔵野女子大学文学部非常勤講師を経て、91年より盛岡大学へ。01年、講師を経て現職。主な共著に『吉野の祭りと伝承』(90年、桜楓社)、『万葉集の民俗学』(93年、同)、『芸術と娯楽の民俗学(講座日本の民俗学8)』(99年、雄山閣)。主な編著に『葛城山の祭りと伝承』(92年、桜楓社)『万葉民俗学を学ぶ人のために』(03年、世界思想社)など多数。
2004年9月号掲載
祭りは人々を結び付ける
──祭りの本来の意味が、分ってきました。
ところで元来、祭りは人々の生活の一部というか、生きていくための拠り所でもあったと思うのですが、現代では、そうした意味合いが変化してきているように思います。ともすれば、観光のための祭りになっている感もある…。
 |
| 岩手県大迫町のあんどん祭り。山車は大迫力 <写真提供:大石泰夫氏> |
大石 観光化が進むこと自体は、多くの人が祭りを喜んでくれることなので、決して悪いことではないと思います。大きな祭りを見物することは、盛り上がりもすごいですし、熱気も楽しめますからね。でも、自分の住んでいる地域の伝統的なお祭りに参加すると、もっと楽しめると思いますよ。
祭りの縁起やいわれを知っていれば、もっと心で感じ、感動も深まると思います。さらに、自分が歌や踊りなどに参加すると、伝統芸能への興味も自然に生れるのではないでしょうか。
──たしかに、地域の伝統的なお祭りを見ていると、みんなで稽古などをするうちに、世代を超えたコミュニケーションも生れ、地域の人々の繋がりが強まっている様子が感じられますね。
大石 そうなんです。祭りの芸能や神輿などを通して、人間が繋がっていくのです。そうした意味でも祭りを理解し、祭りに親しんでいけるような環境が大事です。例えば、小・中学校でそうした教育環境をつくることができるといいですね。
 |
| 盛岡市下太田杉崎八幡宮例祭のお神輿。子供達も積極的に参加 <写真提供:大石泰夫氏> |
──そういえば日本の学校では、あまり邦楽や芸能は教えていないですね。
大石 はい。明治政府は日本の伝統的な音楽や体育を捨て去って、西洋のものを取り上げたわけです。例えば、五線譜の楽譜や海外民謡のフォークダンスのように。
しかし、今は、教育の現場も固有の文化を見直す風潮が出てきていて、独自の授業を創出している学校も増えてきています。体育や音楽の先生が、日本の伝統文化を教えられる日が来ることを望んでいます。
ちなみに岩手県では、小学校の6割、中学校の3割で、例えば地域のお年寄りに頼んだりして、課外授業で伝統芸能を教えているのですよ。県民性もあるのではないでしょうか? その中から、祭りを心から好きになる子供が出てくればいいですね。
 |
| 盛岡県滝沢村のチャグチャグ馬子。美しく着飾った馬たちが街中を練り歩く。大石先生と2人の息子さんも参加 <写真提供:大石泰夫氏> |
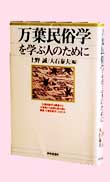 |
| 『万葉民俗学を学ぶ人のために』(世界思想社) |
 サイト内検索
サイト内検索