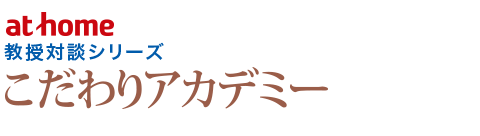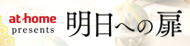こだわりアカデミー
「働かないアリ」がいるからこそ、 アリの社会は長く存続できるのです。
社会の維持に不可欠な「働かないアリ」の存在
北海道大学大学院農学研究員准教授
長谷川 英祐 氏
はせがわ えいすけ

1961年東京都生まれ。大学卒業後民間企業勤務の後、東京都立大学(現・首都大学東京)大学院で生態学を学ぶ。現在、北海道大学大学院農学研究院生物生態・体系学分野准教授。観察、理論解析とDNA解析を駆使して、主に真社会性生物の進化生物学研究を行っている。実験から得た「働かないアリだけで集団をつくると、やがて働くものが現れる」などの研究で話題を呼んだ。著書は、『働かないアリに意義がある』(メディアファクトリー新書)など。
2013年3月号掲載
数多くいる生物の中から「アリ」の生態に引かれ・・・
──先生のご著書『働かないアリに意義がある』を大変興味深く拝読いたしました。アリやハチが、分業的な階層を持ち、集団で生活する「社会性」昆虫であることは知っていましたが、まだまだ知らないことも多く、驚きの連続でした。
アリやハチは、現在「真社会性生物」と呼ばれているそうですが、「社会性」とはどこが違うんですか?
長谷川 「真社会性」とは、集団の中に個体間の繁殖の偏りが存在していることを言います。
例えば、サルは群れを作って「ボス」「見張り役」といった順位制に基づき生活しています。これも「社会」といえますが、サルはどの個体も子を産みます。それに対し、アリやハチは「女王」のみが繁殖をし、その他の個体は巣のために必要な作業を行います。こうした仕組みを備えているものを、学術的には「真社会性生物」と呼んでいるのです。
ちなみに、アブラムシの一部や、哺乳類ではハダカデバネズミも真社会性生物と定義されています。
──なるほど。「社会性」と「真社会性」との大きな違いは、繁殖に関わる分業が確立されているということですね。
ところで、地球上には多種多様な生物が存在しますが、先生はなぜ真社会性生物を研究対象に選ばれたのですか?
|
|
長谷川 もともと、子どものころから生き物の動きを見るのが好きだったんですが、アリに興味を持ったのは、大学2年生くらいの時。イギリスの動物行動学者リチャード・ドーキンスの著書『利己的な遺伝子』を読んだことがきっかけでした。
働きアリは子を産まず、兄弟の子育てを手伝うという「利他」の精神で、自分と同じ遺伝子を後世に残そうとする。それは結果として「利己」的な行動なのだと。ここが非常に面白いと感じ、アリの生態について研究するようになったんです。
──確かに、面白い話ですね。遺伝子によって後世に自己を残そうとする行動は、真社会性生物にも見られるんですね。それに、あんなに小さなアリがどうやって社会を維持しているのか、私もとても興味があります。
アリの世界に存在する「反応閾値(いきち)」とは?
──そういえば、先生のご研究で、コロニー(巣)の働きアリの中には、まったく働かないアリがいることが分かったそうですね。働きアリは全員がずっと働いているものだと思っていました。
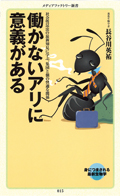 |
| 『働かないアリに意義がある』(メディアファクトリー新書) |
 サイト内検索
サイト内検索