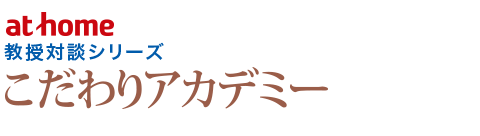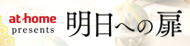こだわりアカデミー
冬眠研究の行く先には、 「不老長寿」をかなえるという 夢があります。
動物の冬眠と長寿の関連性
玉川大学学術研究所特別研究員・薬学博士
近藤 宣昭 氏
こんどう のりあき

1950年愛媛県生まれ。73年徳島大学薬学部卒業、78年東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了、薬学博士。三菱化成(後・三菱化学)生命科学研究所主任研究員、(財)神奈川科学技術アカデミーを経て、現在に至る。大学院修了後、心臓の低温保存研究に興味を持ち、冬眠動物の心臓の低温耐性機能を電気生理学的、薬理学的に研究。この間に、冬眠を制御する生理機能の重要性に気付き、現在、その仕組みの解明を目指している。著書は、『冬眠する哺乳類』(共著、東京大学出版会)、『冬眠の謎を解く』(岩波新書、第27回講談社科学出版賞を受賞)など。
2013年1月号掲載
突然のひらめきで、「冬眠」研究への道が開けた
──先生は、「冬眠」研究の第一人者とうかがっております。また、先生のご著書『冬眠の謎を解く』も大変興味深く拝読いたしました。
そもそも、冬眠の研究者というのはあまり聞いたことがないのですが、先生はなぜ冬眠を研究されるようになったのですか?
近藤 私はもともと薬理学が専門で、心臓移植の可能性を広げるため、大学卒業後から心臓の低温保存についての研究を始めました。
──摘出した心臓を長時間生かすための研究ですね。そういえば、移植手術は24時間以内に行わなければならない、と聞いたことがありますが・・・。
近藤 おっしゃる通りです。それで、移植可能な時間を少しでも延ばそうと、冷やした生理液に実験動物から取り出した心臓を浸して、どうすれば長く保存できるかを繰り返し実験していたのですが・・・。これがちっともうまくいかず、2年もの間、研究は一向に進みませんでした。
そんなある日、ふと思ったんです。「普通、動物は冷やしていくとみんな死んでしまうじゃないか。それなのに、なぜ低温で保存しようとしていたんだろう」と。
 |
──言われてみれば、確かにそうですね。
近藤 実は、この一瞬にしてひらめいた考えが、行き詰まった研究の悩みを一気に解消し、新たなテーマを見いだすことにつながりました。
──それが、冬眠研究を始めるきっかけに?
近藤 そうなんです。この時、体温が下がっても生きている「冬眠動物」が思い浮かんだんです。きっと、冬眠する動物には、何か低温に耐えうる特殊な仕掛けがあり、これが心臓の保存だけでなく、生命維持にもつながるのではないか。これを追求してみたい、と思うようになったんです。この思いに至った時の感激は、今でも忘れられません。
──一瞬のひらめきが、冬眠研究の第一歩になったわけですね。
ところで、冬眠する動物は、どのくらい体温が下がるんでしょうか?
近藤 種類によって違うんです。クマのような大きな動物は、通常の体温(37〜39℃)から6〜7℃くらい下がった31〜32℃にしかなりませんが、リスなどの小動物は、通常の体温(37℃)から30℃以上も下がって5℃くらいになっても生きています。
──本当に不思議ですね。体温が下がっても、凍死せずに生きていられるなんて。人間は、30℃以下になるとほとんど死んでしまうと聞きますが・・・。では、5℃になっても生きていられる仕掛けを探るために、どんなご研究をされたのですか?
  | |
| 冬眠中のシマリス(上)と、冬眠できない環境の23℃で飼育しているシマリス(下)〈写真提供:近藤宣昭氏〉 |
近藤 それには、実験や観測が必要になりますが、まさか穴に潜って冬眠している動物を捕まえてくるわけにもいきませんので、実験室で研究できる動物を探そうと考えました。当時、まだ幼かった息子の図鑑で冬眠する哺乳類を探したところ、「シマリス」が目についたんです。ペットショップでも購入できましたので、これはいいと(笑)。
──そういえば、実験室での冬眠研究にシマリスを用いた研究者は先生が世界で初めてだったとか。
近藤 ええ。しかし、意気揚々と実験を始めたものの、冬眠できる環境を作るのに苦労しました。それでも、ある時からコツを覚えて、成功しましたが。
「冬眠特異的タンパク質」を発見! これが長生きの秘薬?
──同じ環境の中でも、「冬眠するシマリス」と「冬眠しないシマリス」がいるそうですね。
近藤 そのことが、冬眠のメカニズムを解く『驚きの発見』につながったんです。10匹に1匹くらいの割合で冬眠しないシマリスがいたのですが、これらは冬眠するシマリスに比べて短命なんです。
どうして同じ種で違いがあるのだろうと疑問に思い、冬眠するシマリスの血液を調べてみました。すると、血液の中に他の動物にはない特殊な4種類のタンパク質で構成された複合体があり、冬眠する前にこのタンパク質が異常に減少することに気付いたんです。これが冬眠誘発物質なのだろうか・・・。それを確かめるために、冬眠しないシマリスを調べたところ、そのタンパク質の減少は見られず、常に一定だったのです。
これは、冬眠のための特異的なタンパク質なのかもしれない・・・ということで、これらを「冬眠特異的タンパク質(Hibernation-specific protein 略してHP)」と名付けました。
──でも、冬眠に必要ということであれば、逆に増えるのでは?
近藤 そのように考えるのが普通ですよね。でも、別のところでちゃんと増えていました。血液中で減少したHPは脳内に運ばれ、活性化されて増加していたんです。
──つまり、その仕組みが「冬眠に入れ」というシグナルだと?
 |
| 10畳ほどの低温室に設置した、体表面温度自動計測システムの一部。近藤氏のアイデアで特注した機器で、世界に1つしかないという〈写真提供:近藤宣昭氏〉 |
近藤 はい。私はHP複合体の増減こそ、冬眠のメカニズムだと考えています。
さらに、冬眠できない環境の23℃でシマリスを飼育してみたところ、一部早死にしてしまったシマリスもありましたが、ほとんどが冬眠するシマリスと同じ寿命を維持していたんです。そして調べてみたところ、長生きしたシマリスにはHPの増減が起こっていて、早死にしたシマリスには起こっていませんでした。つまり、長寿の秘訣は冬眠することではなく「HPの増減」だと考えられるのです。
──それはすごい! 先生が発見したHPは、「長生きの秘薬」になるかもしれないというわけですね。
近藤 その可能性は大いにあると思います。
それに、冬眠する動物は病気をしないんです。例えば冬眠中のクマは、筋肉がほとんど萎縮・退縮しませんし、骨粗しょう症も起こりません。HPの増減が起こっているシマリスは、不思議とがんにもならないし、脳いっ血や心筋梗塞にもならないんです。
HPさえあれば、ヒトも長生きできる?
──本当ですか!? では、HPがヒトにも適用できるなら、不老長寿も夢ではないと・・・。
近藤 そうなるかもしれませんよ。実は、すでにラットを使って長生きさせる実験を始めているんです。最終的には、ヒトの冬眠を可能にしたいという夢もあります。誰もやっていないことをやるのが、昔から好きなんです(笑)。
とにかく、シマリスの長寿には、HPによる仕組みが備わっているからだということは疑いようのない事実ですから。
 |
| 23℃の冬眠できない環境のスチール棚で飼育されているシマリス。体温は常にほぼ37℃を保っている〈写真提供:近藤宣昭氏〉 |
──この仕組みを解明すれば、そう遠くない将来、われわれは冬眠することができて、さらに長生きできる時代が来るかもしれないんですね。
近藤 そういう時代が来るよう、これからもがんばります!
──ワクワクしますね。そんな日が来ることを心待ちにしています。
本日はありがとうございました。
 |
| 『冬眠の謎を解く』(岩波新書) |
 サイト内検索
サイト内検索