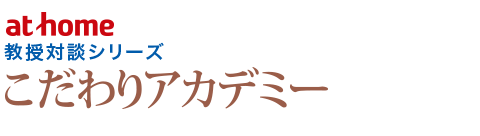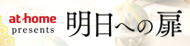こだわりアカデミー
選択する側の生物が間違いをするから進化が起こるんです。
生物のサバイバル戦略−共進化
立教大学理学部助教授
上田 恵介 氏
うえだ けいすけ

1950年、枚方市生れ。大阪府立大学で昆虫学を学んだ後、大阪府立大学理学部大学院に進み、鳥類学を専攻。三重大学講師を経て現職に。理学博士。小学校時代から日本野鳥の会に所属する、生粋のバードウォッチャー。95年はオーストラリアのダーウィンでセアカオーストラリアムシクイという小鳥の研究に費やし、現在もこの研究は進行中。著書に『一夫一妻の神話−鳥の結婚社会学』(87年、蒼樹書房)、『鳥はなぜ集まる−群れの行動生態学』(90年、東京化学同人)、『♂♀のはなし−鳥−』(93年、技報堂出版)、『花・鳥・虫のしがらみ進化論−「共進化」を考える』(築地書館、95年)がある。
1997年1月号掲載
お互いがお互いを進化させるのが「共進化」
──「共生」という言葉は最近よく耳にしますが、先生が研究されている「共進化」とはどういうものなんでしょうか。
上田 生物というのはお互いが関係を持って生活しているわけです。生きるためには餌を食べなければいけないし、反対に襲われないように逃げて生き延びねばならない。その場合の相手というのもやはり生物です。ですから食べるものに対しても適応しなければならないし、またうまいこと逃げられるようにも適応しなければならない。進化はそこで起こるわけですが、進化するのは自分だけじゃないんです。食べられるものも襲うものも進化していく。
例えば、シマウマとライオンの関係でいうと、シマウマは走るスピードが非常に速い。ライオンは鋭い爪や牙があり、ものを捕まえる能力に非常にたけている。しかし、ずっと昔のシマウマやライオンは今ほど速くも強くもなかったはずです。そういった中でライオンも楽をしたいという場合、足の遅いやつを捕まえますよね。そうしていくと足の遅い遺伝子は集団からどんどん消えていって、速いものが残っていく。ライオンが楽をしようとすればするほど、シマウマは足が速くなるという、ライオンには矛盾した結果ですが、ライオンだって、このままじゃいけない。素早く知能を働かせて、さらに爪や牙も強くしなければならない。この繰り返しが共進化、お互いがお互いを進化させるという考え方です。
──ライオンとシマウマだけでもそうですが、その周辺、他の動物とか植物とかを入れてもやはり同じような関係が存在しているわけですね。
上田 ええ、シマウマと雑草にもあります。雑草としても全部食われてしまったら絶滅するわけです。そんな中で生き延びる性質を進化させてきた。これはシマウマと雑草の共進化です。
果実が果肉をつけたのは鳥やサルをおびき寄せるため
──植物とそれ以外の生物にもやはり「共進化」が起こるわけですか。
上田 もちろんです。例えば、果実にはいろんな色や大きさ、味がありますよね。モモやリンゴなどの甘くて大きな果実は、人間が長い栽培の歴史の中で改良を重ねていったものですが、ヒトがいなかった時代、それらの原種は小さくて甘味も少なかったでしょう。じゃあ、それらが何のために存在していたのかというと、鳥やサルたちをおびき寄せるためです。
──種を運んでもらうために?
上田 植物の中には、さやがはじけて種子を遠くへ飛ばしたり、風に頼って分散を図るのもいます。これらの方法だと、あまり重い種子をつくるわけにはいきません。しかし、軽い種子では発芽率、定着率も悪くなります。種子のために十分な養分を蓄えてやること、遠くへ分散させること、動けない植物がこの相反する矛盾を解決するために生み出した方法が、鳥やサルを引き寄せるための果肉をつけることだったのです。そして、甘くしたり、ちょっとでも目立つ色にすればあちこちに運んでもらえます。
野山を歩くと緑や茶色の実よりも赤い木の実が多く目につきますよね。あれらも鳥に種子を運んでもらうために、果肉をつけ、目立つような色になっていったんです。また赤い色にはもう一つ効果があります。赤は鳥には見えやすく、種子を食害する昆虫には見えにくい色なので発見されにくい。もし、発見されたとしても鳥が食べにやってきてくれるわけです。
──その鳥も、他の生物の餌になるわけですよね。そういった天敵から逃れるために、鳥自身も、何か工夫したりしているんですか。
上田 そうですね。特徴的なものをあげれば、そ嚢という器官が発達しています。これはくちばしのすぐ近くにあり、一時的に食べ物を貯蔵しておく器官で、鳥は自然界には天敵がたくさんいますから、食べ物が見つかるととにかくここに詰め込み、安全な場所に行き、胃の方に徐々に送っていって、ゆっくり消化するというシステムです。
それから周りの鳥を追い払うために、鳥同士でも警戒音を似せている例もあります。シジュウカラとかヒガラの種がそうです。例えば天敵が現れていないのにピッと鳴いたら、自分たちの仲間の声だと思ってびっくりして逃げる。逃げたところでゆっくり食事をする。まさにだましだまされの世界ですよね。
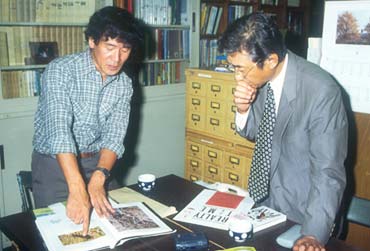
人間に踏まれないためにイヌの糞に擬態したナメクジも
──だましだまされるというと虫の擬態を思い起こしますが、これも共進化のひとつと考えていいんでしょうか。
上田 その通りです。そしてその擬態をつくり上げていったのは、昆虫食の鳥たちなんですよ。
例えばチョウの中に毒のあるのがいるんですが、それとは種類は違うが少し似ているのもいます。鳥の方はというと、そのチョウに毒があるのは分かっている。こっちの方も毒のあるのに似ているからやめておこうか、といった具合に、選択する側が間違いをするから、似ていないものよりもより似ているものの方が生存率が高くなり、どんどん進化していく。
──あのコノハムシにいたっては完璧ですよね。
ヨーロッパにはイヌの糞に擬態したナメクジがいるそうですが…。
上田 初めて見た時は、ほんとにギョッとさせられました。最初は冗談で考えついたんですが、よくよく考え直してみると、やはりあれは人間に踏まれないようにしたナメクジの知恵なんだと思います。
──どんなものなんですか。
上田 割と大きいです。大きさは親指くらいありますから、10−p近いと思います。ちょうど中型犬の糞と同じくらいですね。色も少し赤っぽい茶色と、黒に近い焦げ茶色と2種類あります。
この2種類あるのも意味があるんじゃないかと思います。一つなら恐らく見破られてしまうけれども、2種類が混ざって存在することによって撹乱できる。こっちはナメクジかも知れないけど、こっちは本物かも知れないとか、つい迷わされてしまう、というのはかなり効果的な意味を持っているわけです。
──人間も選択者なんですね。
上田 ですから、人間も進化を促す役割を持っているんです。
スズメ目が現れなければ昆虫はここまで多様化しなかった
──今までのお話を伺っていると、生物の持っている機能を全て駆使して生き延びるための大戦略をとっているわけですね。同じ種族ならともかく全くの異種にまで似てしまうなんて、何とも不思議です。
上田 本当にそうですよね。これは先程話が出ましたが、選択する側の生物が間違いをいっぱいするからです。
まねをした昆虫は最初から正確な模様をつくったわけではなく、マダラ模様だったりした。しかし鳥も無難な生き方をしているから、毒虫で一度痛い目にあったり、目玉模様で驚かされたりすると、危ないものにはなるべく近寄らないようにしようとする。熱帯の方では鳥だけでなく小さいサル類も虫を食べていますが、こと虫の進化に関しては鳥類の中でもスズメ目の影響が大きいんです。
鳥の種は世界で9,600種ぐらいいますが、そのうち5,000種がスズメ目で、カラスもここに含まれています。
このスズメ目は鳥類の中でも一番新しいグループなんですが、今こんなに世界中でスズメ目がはびこっているのは、恐らく記憶力とか状況を認知するいろいろな能力が他の鳥と比べかなり優れているからでしょう。ですから、なおのこと危ないものには近づかない。このスズメ目が現れなかったら、昆虫の世界もこんなに多様性のあるものにならなかったんじゃないでしょうか。
──生存率を高めるということは、そういう選択者のちょっとしたミスをうまく利用していくことであり、それが進化につながっていくんですね。
上田 ええ、特に何か目的があるわけじゃないんですが、ちょっとでも生存率が上がる方向があれば思いきりそちらの方へ進んでしまうんです。
ただ、擬態にしろあそこまでつくり上げるのには何十万、何百万年という時間がかかっているわけです。私たちは、こんなに素晴らしい器官が発達しているのか、こんなに似ているのか、とその結果だけを見てしまいがちだから、神様がなんかの目的でつくったのかとつい思ってしまいます。ですから、私たちが進化学を学生に教える場合、人間が時間をどうとらえているか、そこの部分を教え込むところから始めるんです。そうしないと、単に「進化というのは不思議な現象だな」、で終ってしまう。
しかし、これは決して不思議なことではなく、共進化ということを考えれば多くの疑問が解決できます。生物の世界ではこうした長い年月の中で、お互いがお互いの能力に磨きをかけて、生き残りを図っているわけです。
──長い年月から見れば進化も当たり前のことなんですね。もしかしたら人間だって他の生物が間違った選択をした結果進化した生物なのかもしれない、とふと思いました。
今日は共進化のさわりをお聞かせいただきましたが、進化は決して一方だけに起こるものではないことがよく分かりました。オーストラリアで次の研究に取り掛かっておられるそうですが、素晴らしい成果を期待しております。ありがとうございました。
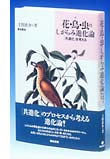 |
| 『花・鳥・虫のしがらみ進化論 「共進化」を考える』(築地書館) |
現在は同大学の教授に。また近著に「擬態−だましあいの進化論−1、2」、「種子散布−たすけあいの進化論−1、2」がある(いづれも築地書館より発行)。
 サイト内検索
サイト内検索